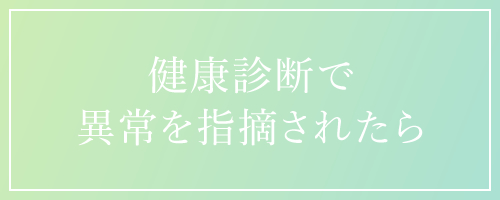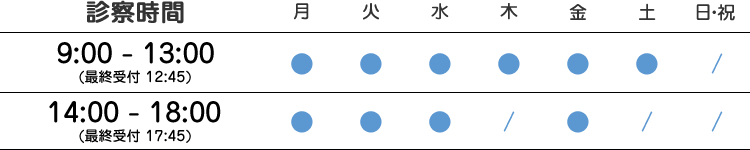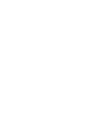福岡市西区愛宕浜の内科・循環器科「阿南クリニック」
- 唐突ですが当院に通院されている方、待合室に掛けている『青春』という詩を読んだことがあるでしょうか?
(当クリニック 待合室にて)

(左:婦長、右:母、写真:前院長)
実はこの詩、26年前に前院長が開業した当時から掛けているんです。
私が初めにこの詩の存在を知ったのは、幼稚園児の時でした。今は亡き母方の祖父の家の居間に、賞状サイズの筆書きで、幼稚園児だった私が椅子に登れば見える高さに掛けてありました。
- 祖父の家は幼少の私にとってはお城のようで、珍しい物(古き良き昭和初期に日常使用していた品々)が沢山あり、遊びに行く度に宝物探しのようにワクワクしながら扉を開けて色々な物を眺めていました。当時は『青春』が視野の中にあることを意識せずに…。
時が経ち、前院長が当クリニックを開院する時、『あの詩を待合室に掛けたい。』と言ったので、祖父が特別に注文して 父にプレゼントしてくれました。小学4年生に成長した私は、あの筆書きの『青春』が掛けてある祖父の家の居間にいるような心地で、新しくプリントされた大きな額縁に入っている『青春』を改めて読みました。
そして今、あの頃と比べて確実に歳老いてはいるけれど、真に老いたくはないと、随所に思います。医師として毎日患者さんと向き合っていると 患者さんから教えられることが多々あり、それらが私を叱咤激励してくれるからです。
例えば、関節リウマチで手がとても痛いのに、いつも笑って、最近、英語の勉強とピアノを始めた70代の患者さんがいます。
例えば、数年前に息子さんを亡くされた60代の女性は、高血圧症の治療のため、傍目には変わらず今まで通り明るく優しく上品な雰囲気のまま、当院に通院されています。
例えば、大動脈炎症候群で心臓移植待ちだったの50代の患者さんは、心不全入院を繰り返す度に、いつも私に歴史の講義をしてくれました。
例えば、重症心不全でCCUに入院していた20代の患者さんは、命が尽きる間際まで、母親を気遣っていました。
そういう患者さんと対峙する度に、素直に、私も頑張ろう!と精神が若返る心地です。
因みに、ここ数年の間で特に印象深い患者と言えば、やはり 亡くなってしまった私の父親でしょうか。
当クリニック前院長 阿南健(父)は、肺癌の脳転移が発覚した入院前日の夜、身体をフラフラさせながら書斎でカルテの整理(いつもの仕事)をしていました。そして入院中も、出来る限り 当院スタッフと電話のやり取りをしながら仕事を続けていました。その傍ら、病室には趣味のカメラとフライフィッシング(釣り)の道具を持ち込んで眺めていました。
父は最終的に私の勤務している病院に入院していたので、父の病室は 私の仕事の合間の休憩場所にもなっていました。私は白衣姿で父の病室を毎日 出入りするようになり、また、当直の時を含め度々、父の病室のソファで寝泊まりしていました。
その時の父との会話の内容は 家での親子の会話と変わらない感じで、この薬はどうだとか、この症例はああだとか、同職業どうし医学的な内容の お互い興味のある楽しい話が主でした。
父は既に肺癌の多臓器転移の状態だったので、父が父親として見せたくないであろう弱っている姿や、私が娘として見るに絶えない症状を目にすることも、当然 多々ありました。夜中のシンとした病院の中で、電子カルテ内の父の悪化している画像所見や検査所見を見ながら、自然と涙が溢れることもありました。
しかしそんな状況の中でも、父は治って仕事に復帰するつもりでいたので、積極的に抗ガン剤治療を行いました。
一方でモルヒネ(強い鎮痛薬)を投与しても痛みを訴え続け、徐々に痛みで身の置き所が無くなってくる父…。私は医者として無力さを感じながら、そして医者なら父の苦痛を取り除くために鎮静をかける(強い睡眠薬を投与する)べきだと思いながら、躊躇していました。現状を診れば、鎮静をかけたら もう父は永遠に目覚めないという確信があり、一方で 娘の我儘として、まだ父と言葉を交わしたかったからです。
一日の勤務終わりに父の病室に行くことが日課になっていた私は、ある日 いつものように深夜の寝静まった病棟を歩きながら父の病室へ向かいました。
消灯した病室のドアを静かに開けると、薄暗い中、シューシューと酸素投与の機械音だけが聞こえます。点滴の投与速度とか酸素投与量とかバイタルなどの確認をして、そっと父を覗き込むと、ハタと父が目を覚ましました。『沙織、まだ病院にいたのか。何時だ?ちゃんと帰れ。』と。そして他愛もない会話をしていたら、すぐに痛みを訴えてきました。
私が起こしてしまって目を覚ましたのではなく、痛みで眠れていないのだろうと直感し、背中に冷たいものが走りました。
段々 いつものように父が息苦しそうになってきたので、すぐに吸引して酸素投与量を増やして…。私が平静を装ってあれこれ対応している最中、父はハアハアと深い呼吸をしながら横向きになって、ベッドの柵をギュッと掴みながら『沙織、もうダメかな?』と、薄暗い病室に酸素投与の機械音がこだまする中、静かに言いました。
初めて聞いた、弱音とも諦めとも懇願ともいえる父のこの一言は、一生、私の耳から離れないと思います。
少し落ち着いた父が『もう寝る。沙織も帰れ。』と言い、しばらくして小さなイビキをかき出したので、音を立てずにそっと病室を出ました。
再び 深夜の寝静まった病棟を歩きながら、『明日、父に家族の顔を見せて、それから鎮静をかけよう…。』そう決断しました。
それから数日後、普段通り休日の病棟で仕事をしていた時、白衣のポケット内のPHSが鳴ったので、普段通り手探りでポケットから取り出してPHSを耳に当て、『はい、阿南です。』と応答しました。父の主治医からの電話でした。父の脈拍数が落ちてきたとの報告でした。
最期だ…。
すぐに父の病室に走りました。この時ばかりは『阿南先生、ちょっといいですか?』と私を呼び止める看護師の用件を後回しにし、予定していた受け持ち患者の回診も後回しにしました。
焦って父の病室のドアを開けると、家族皆が父を囲んでおり、母がしきりに父の名前を呼びかけていました。すぐに父の胸に聴診器をあてると、鼓動がだんだん遅くなっていきました。しばらくして、何も聞こえなくなりました。ベッド上の父を囲む家族皆の前で 父の死亡確認をした私は、医者だったのか娘だったのか、よく分からない感覚でした。
今でも たまに待合室に掛けている『青春』や、廊下に掛けている父の写真を見つめます。一介の開業医だった父だけれど、少なくとも私には最高の先輩だったな と思いを馳せ、死してなお、今後の私の医者人生に影響力のある一人であり続けるんだろうな としみじみ思い、父は最期まで青春の中にいたと確信しています。

(右:前院長 ※当院廊下の写真より)
人生には、思いがけない事が起こる。
人はいつでも、生と死の狭間に立っている。
病を抱えている患者さんを相手にしていると、生きている間は生きる事が責務だと思わずにはいられません。
老いて病んで体が言うことをきかない辛さは、私も誰しも一度は経験していることだと思います。けれど、それを払拭して余りある精神で、意味のある一生を得たい。
たくさん感動できるように、より多くの知識と言葉を得るよう努める。安心や温かみを感じるために、人や動物と触れ合う。確かな満足感を得るために、自分と家族と社会に 出来る限り貢献する。教育や情や助けなど、有り難く得たものは他者に還元する。
歳老いた今からでも、やれる事を精一杯やろうと思います。青春を謳歌するために。